〜終わり〜
■ぜひアンケートにご協力下さい■
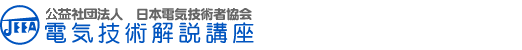

電力ケーブル故障点の測定法の主なものは3種類である。
線路定数を測定するマーレーループ法と静電容量法が測定も容易で、測定精度も高い。この2種類でほとんどの故障点測定が可能なので、ここではこの2方法について解説する。
もう一つの方法であるパルス測定は断線故障で、特に対地、線間の故障抵抗が小さい場合(低圧パルス法)または地絡故障で地絡抵抗が極めて大きく、かつ故障点の炭化が困難な場合(放電検出法)に採用される。しかし、故障点の波動インピーダンスが電力ケーブルのそれに近づくと原理的に測定不能になる。また、高度の測定器と技術を必要とする。
いずれの測定法も線路の実長を基礎に算出するので、その正確な把握が重要である。
故障の状況によって適用する測定法が異なるため、測定開始前に端末からの各相絶縁抵抗(地絡、短絡抵抗)測定、導通試験で十分に確認しておくことが特に重要である。
この測定法はホイートストンブリッジの変形で、地絡相と健全相を相手端で短絡し、ループの抵抗と故障点までの抵抗の比を測定するものである。
第1図に回路図を示す。図のような目盛配置で、目盛![]()
![]() で平衡した場合、ケーブルサイズが全長同一であれば、故障点までの距離
で平衡した場合、ケーブルサイズが全長同一であれば、故障点までの距離![]()
![]() は線路の全長を
は線路の全長を![]()
![]() 〔m〕として次式で求める。
〔m〕として次式で求める。
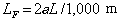
異なるケーブルサイズが接続されている場合はどれか1種に換算したうえで算出する。
例えば、測定端から150mm2が300m、100mm2が250mのケーブルで、![]()
![]() = 220で平衡したとすれば150mm2に換算した全長は、
= 220で平衡したとすれば150mm2に換算した全長は、
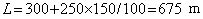
故障点までの距離は、
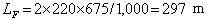
となり、両サイズの接続箇所が疑わしく、解体調査に入ることになる。
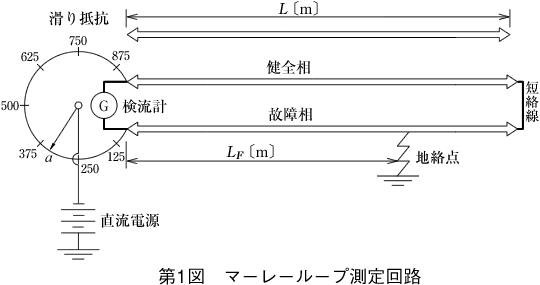
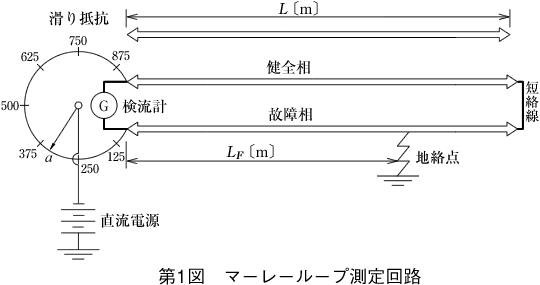
電力ケーブルの故障は大部分が1線地絡であり、この測定法は最も多く使用され、測定精度も1%以下と高い。
測定のために50〜100mA程度の安定した直流電流が必要であり、故障点の地絡抵抗が極度に大きいか、不安定な場合には電圧をかけて、故障点を炭化しなければならない。このため、出力電圧0〜1,000V程度の可変電圧直流電源(整流器)が使われる。また、炭化の過程で異常音を発するので、管路式、暗きょ式線路ではマンホール内の点検で、ラック敷設ケーブルではルートの点検で発見することもある。
水場布設や地絡抵抗が小さい場合や炭化が完了したときは電源は数Vの乾電池で足りる。
マーレーループ測定器は構造が簡単なので手製できる。これで測定精度も実用上十分である。用意する材料は1mの物差し(竹、プラスチック)と![]()
![]() 1〜2mmのマンガニン線を余裕をみて1.4m程度、それに若干のリード線、クリップである(第2図)。
1〜2mmのマンガニン線を余裕をみて1.4m程度、それに若干のリード線、クリップである(第2図)。
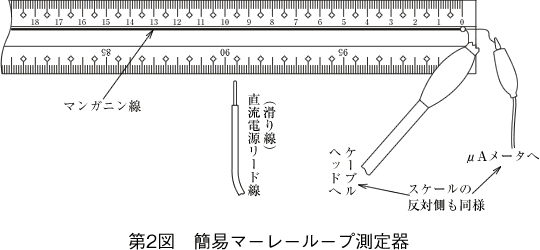
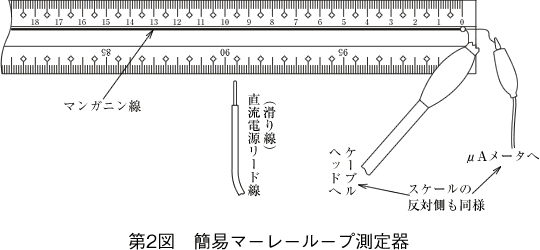
まずマンガニン線を物差しに貼り付けるが、竹製の物差しには溝が掘られているものが多く、ここへ貼り付ければよい。接着剤が硬化したらマンガニン線の表面を細かいサンドペーパーで磨いておく。
ケーブルヘッドへのリード線はケーブルの一部とみなされるので、太いものを使用し、できるだけ短くする。全体の抵抗が小さいブリッジなので、相手端の短絡線やリード線の接触抵抗に注意を要する。
検流計としてはテスタのμAメータで代用できるが、感度の高いものが良い。
マーレーループ法では健全相があることが必要であるが、線路が短距離の場合には健全相の代わりにルート上に補助線を延線することにより、非断線の三相故障の測定ができる。補助線の太さはできるだけ測定するケーブルの心線に近いものが良い。ケーブル心線と太さが異なる場合はループの全長をケーブル心線の太さに換算する。
すべての心線が断線している場合、あるいは非断線相が残っていても、補助線の敷設ができないときはマーレーループでは測定できない。
この場合には市販の直読型の静電容量計によって心線の対地静電容量を測定する方法が簡単である。現在では小型のテスタでも、外部交流電源を利用して静電容量が測定できるものが多い。
故障点までの距離は次式で表される。
この測定では測定端、相手端で測定相以外をすべて接地して、無用な静電容量を混入させないことが重要である。
この測定は比較測定であるから絶対精度は高度に要求されず、また故障点の地絡抵抗は測定器にもよるが、100Ω以上あれば実用上測定できる。
異種ケーブルが接続されている場合はそれぞれの標準静電容量によって補正する。測定レンジはケーブルの種類、太さによるが、6kVCVケーブルで0.5Μ/km程度とする。
以上実用的な電力ケーブルの故障点測定法について述べたが、マーレーループ測定器は特別高圧受電で構内に高圧ケーブルをたくさん使用している場合など一つ作っておくのも役立つと思う。
また、地中電線路(電力ケーブル)故障点測定の全般技術については本シリーズの「地中電線路の故障点測定」を参照されたい。
