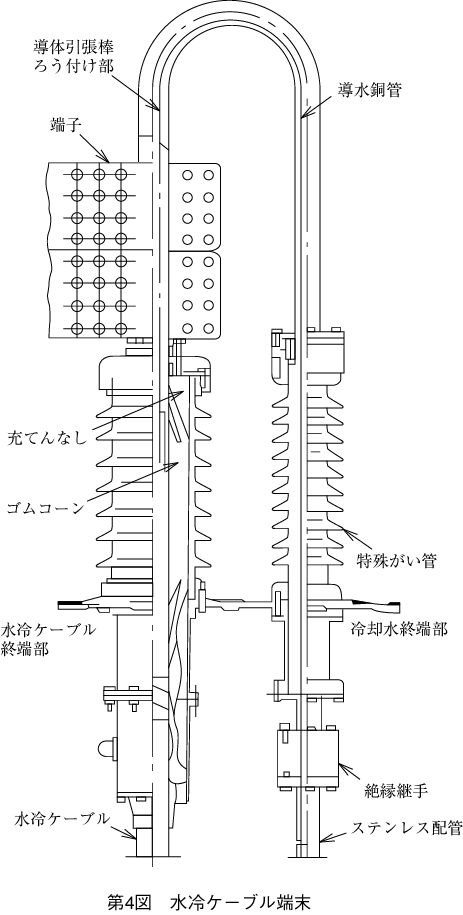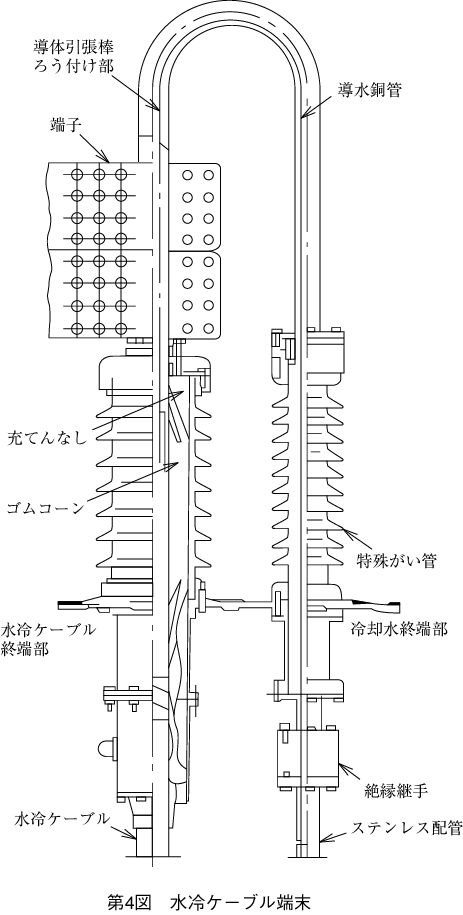〜終わり〜
■ぜひアンケートにご協力下さい■
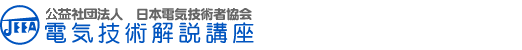

初期のころの管路引入れ用ケーブルは鉛被上に防食層がなかったため、電食対策として二重鉛被が施されたりした。都市部の電食はほとんどが直流電気鉄道によるもので、埋設ケーブルが軌道から離れる場所などに発生し、その区域は限定される。電車線側を陽極にするのはこの理由によるもので、反対にすると電車の移動に伴い軌道付近がすべて電食地帯になる。
対策はいろいろあったが、選択排流器と流電陽極が主として採用された。前者は埋設ケーブルからの電流を土壌に流さず、信号用のインピーダンスボンドを利用して、その中性点から直接レールへ返すもので、電流容量は50〜600Aであった。
後者は鉛より卑金属であるマグネシウムを陽極としてケーブルに接続して埋設し、その電池作用によって防食効果を図るもので、陽極は消耗するので適時補充していた。
当初の管路は鉄管であったので、引き入れた管路内の鉛被ケーブルは鉄管の遮へい効果によって30年以上経って撤去したものにも腐食は見られなかった。
1950年代になり、クロロプレン(ネオプレン)に代表される人造ゴムやPVCなどによる防食層が鉛被上に施されるようになり、電力ケーブルの電食対策は解決した。ただし、後述するPOFケーブルではその高油圧による重要性から、鋼管に対する外部直流電源による電気防食などが行われている。
電食関係技術の詳細については、電気技術解説講座「電食のはなし」を参照されたい。
遮へい形ケーブルでは絶縁紙にかかる沿面ストレスはなくなり、介在物は電界の外になったが、負荷変動による絶縁体内のボイドの発生と、それに加えて敷設ルートの高低差による絶縁油の流下は避けられず、より以上の高電圧ケーブルとしては性能上不十分であった。これの解決のため圧力ケーブルが考案された。
1917年(大正6年)イタリアでOFケーブルが発明されて、1923年(大正12年)アメリカ・クリーブランドに単心66kVケーブルが敷設され、翌年ミラノ、ニューヨーク、シカゴに132kVケーブルが敷設された。
我が国では1928年(昭和3年)単心66kVOFケーブルが熱海に敷設された後、66kV、77kVOFケーブルが各地に敷設され、1958年(昭和33年)には154kVOFケーブル、こう長10kmが東京に敷設された。
OFケーブルは特に粘度の低い絶縁油をケーブル内に含浸封入し、給油用油槽によって内圧を常に大気圧以上で、かつ一定範囲に保つもので、ボイドの発生、絶縁油の流下による絶縁紙の含浸不良を完全に解決しており、以後、高電圧ケーブルの主流になった。製造方法もソリッドケーブルと異なり、被鉛した後、真空含浸している(第1図(a))。
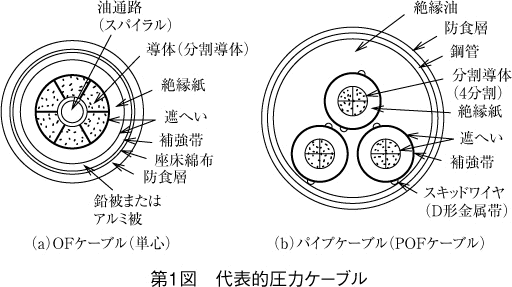
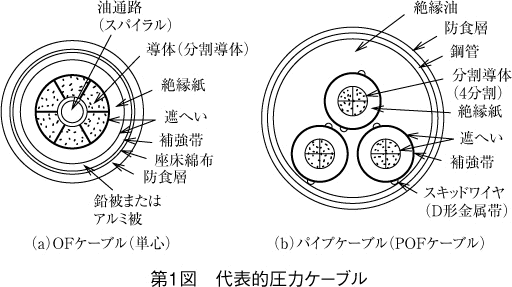
油槽には高所に設置し、落差によって圧力を加える重力油槽(FT)、 封入ガスの圧力による圧力油槽(PT)、 封入ガスを所定範囲に制御する特殊圧力油槽(SPT) があり、いずれもバルブパネルや漏油警報装置が付帯し、漏油に対する給油までの余裕油量をもっている。
長距離線路では負荷の投入遮断時などの過渡油圧変化から、数kmごとに給油区間を区切らなければならず、給油設備が大きくなる。
1933年(昭和8年)GFケーブルが発明された。構造はHケーブルを脱油し、介在部に通路を作って窒素ガスを封入したもので、我が国での採用はわずかであった。
また、1960年(昭和35年)ごろフラット形OFケーブルも採用された。構造は三相線心を横一列に配置した扁平形のケーブル目で、油槽が不要であり、絶縁油の収縮はケーブル断面の変形で対応した。
OFケーブルは現在超高圧線路に広く採用されている。
OFケーブルは圧力を高くすると絶縁耐力、特に交流耐電圧が向上する特性があることから、OFケーブルの線心三相3条を防食鋼管に引き入れ、2MPa程度の絶縁油を充てんしたPOF(パイプ形OF)ケーブルが1935年(昭和10年)に開発された。
このケーブルは現在の電力ケーブル中、最も絶縁特性の優れたものである。線心にスキッドワイヤが巻いてあるので、鋼管との摩擦が小さく、長スパンの引き入れが可能であり、また鋼管内の絶縁油を循環冷却して送電容量を増大することができる(第1図(b))。
電力ケーブルの黎明期には非加硫の天然ゴムで絶縁したケーブルが使用されたこともあるが、1953年(昭和28年)に3〜15kVのBNケーブル、EPケーブルが我が国各地で敷設された。
BNケーブルはブチルゴム絶縁、ネオプレン(クロロプレン)防食ケーブルで軽く、特に耐水性に優れたため、その後22〜44kVの海底ケーブルに採用されることが多かったが、経済的な理由などから一般線路としてはCVケーブルに替わられた。
EPケーブルはエチレンプロプレン絶縁ネオプレン防食ケーブルで、電気特性が良く、特に耐トラッキング性、屈曲性に優れているので、22〜44kVの電車用、移動用ケーブルとして現在も使用されている。
1939年(昭和14年)ネオプレンとともにポリエチレンが合成され、電力ケーブルに使用された。ポリエチレンはその後耐熱性を向上された架橋ポリエチレンに替わった。
我が国では1965年(昭和40年)ごろ3kVで採用され、現在低圧から500kVまで広く使用されており、2000年(平成12年)には500kVこう長40kmのCVケーブルが東京に敷設された。
絶縁特性は良好で、誘電率、誘電損失ともに小さく、高電圧ケーブルに適しているが、繰返しインパルス特性がOFケーブルより劣ること、透水性が必ずしも解決していないことなどがあり、絶縁厚はOFケーブルよりも大幅に大きかった。
最近では絶縁物への微小異物混入の徹底的な排除によって超高圧ケーブルでは絶縁厚みの低下が図られ、透水性については66kV級以上では防食層の下に鉛ぱくによる遮水層を施し、地絡電流の帰路として遮へい層全周に1.2mmの銅線を沿わせている。
220kV以上では遮水層と地絡電流帰路の両者を兼ねてアルミニウム被服としている。
CVケーブルにはOFケーブルのような油槽などの付帯設備がなく、保守上有利である。
曲げ剛性がほかのプラスチックケーブルより大きいため、66kV、400mm2程度以下はトリプレックス形(CVT)として曲げ特性を改善している(第2図)。
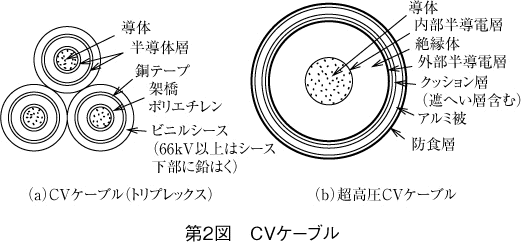
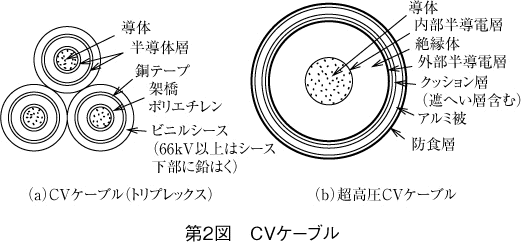
(a) 管路気中送電(GIL)
導体にアルミニウムを使用し、これをエポキシ樹脂製の絶縁スペーサでアルミニウム管またはステンレス管(シース)内に同心配置し、0.5MPa程度のSF6ガスを封入したものである(第3図(a))。
1969年(昭和44年)ニューヨーク市に345kV送電容量2GVAのものが敷設され、我が国でも1980年(昭和55年)275kV、1985年(昭和60年)500kVのものが敷設された。
管路気中送電の比誘電率は1で、誘電損失も無視できるため送電容量が大きく、2導体の架空送電線の許容電流に匹敵する電流容量が確保されることから発変電所の引出し口などに採用されている。
このケーブルは構造上、導体とシースの伸縮対策が工夫されている。
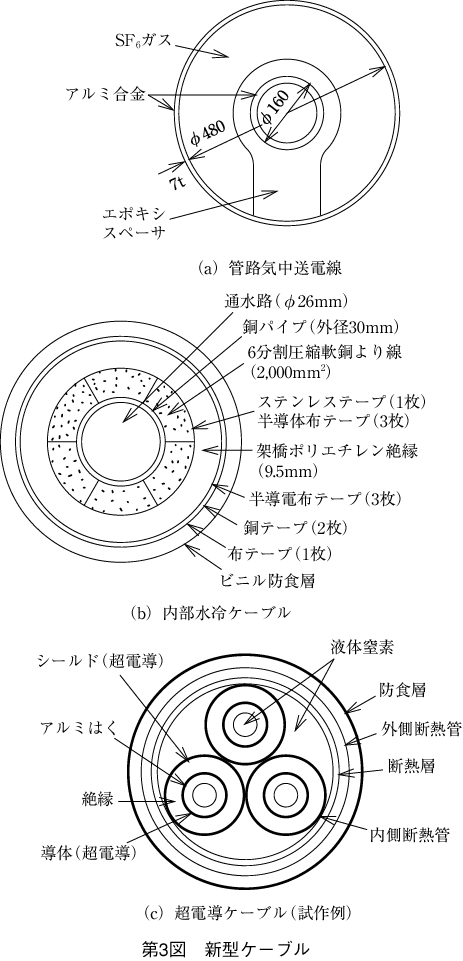
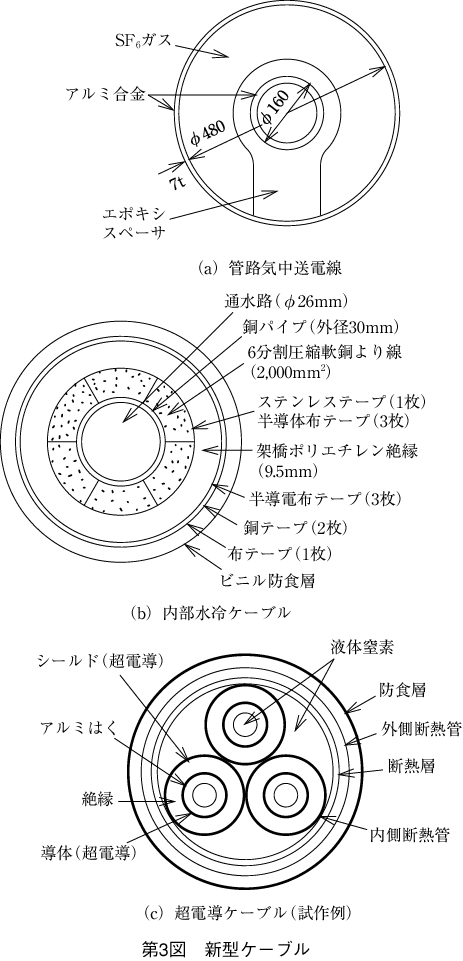
(b) 内部水冷ケーブル
ケーブルを冷却して送電容量を増大することは大送電容量を必要とする高電圧ケーブルで行われ、その方法もいろいろあるが、内部水冷ケーブルは発生熱の根本である導体を直接冷却するため、送電容量の増加は特に大きく、大容量揚水発電所の主幹ケーブルとして採用された例もある(第3図(b))。
この方式ではイオン交換樹脂を使用した水質の徹底した管理と、ケーブル内の冷却水の循環方法に工夫がされている。第4図に端末部の例を示す。
いずれの方式でもケーブルを冷却して送電容量を増大する方式では、冷却装置の故障時には直ちに負荷制限が必要になり、冷却装置の信頼度がそのまま線路の信頼度になる。
(c) 極低温、超伝導ケーブル
高純度の銅、アルミニウムは数十Kの極低温になると電気抵抗が常温の1/10程度になる。また、ある種の金属は同程度の低温で、電気抵抗がなくなる超伝導状態になる。この特性を利用した大電流ケーブルの開発研究が進められている(第3図(c))。
現在は比較的短距離ケーブルの試作研究の段階であるが、長距離化が期待されている。