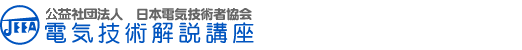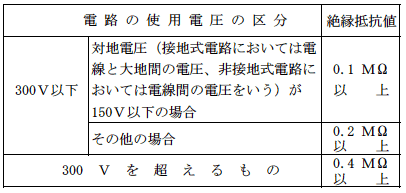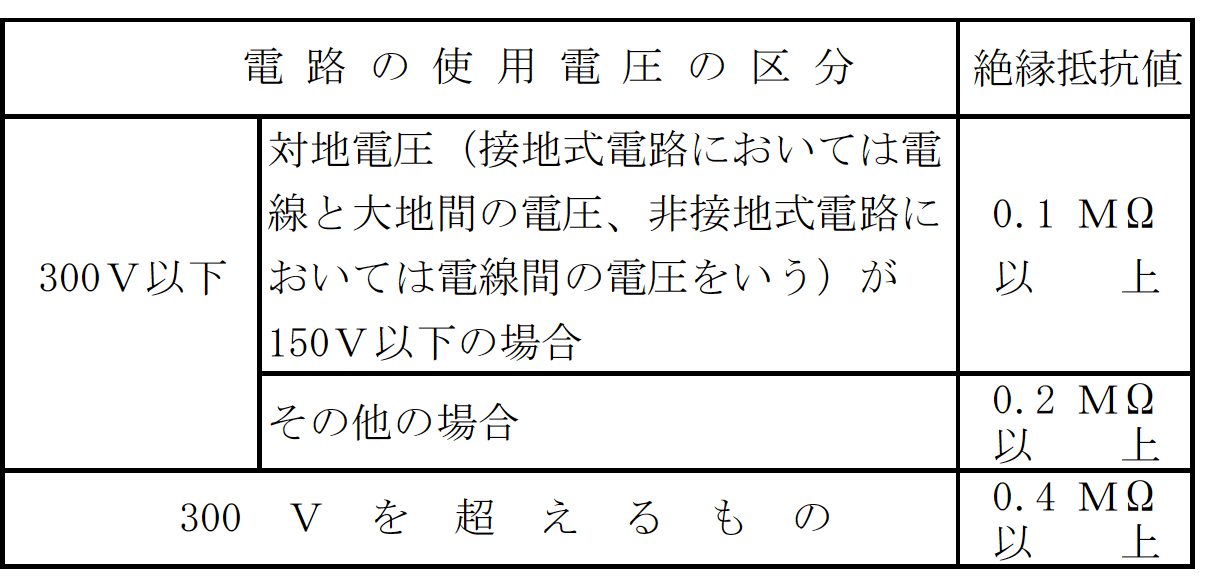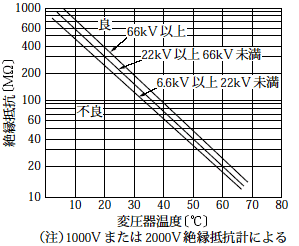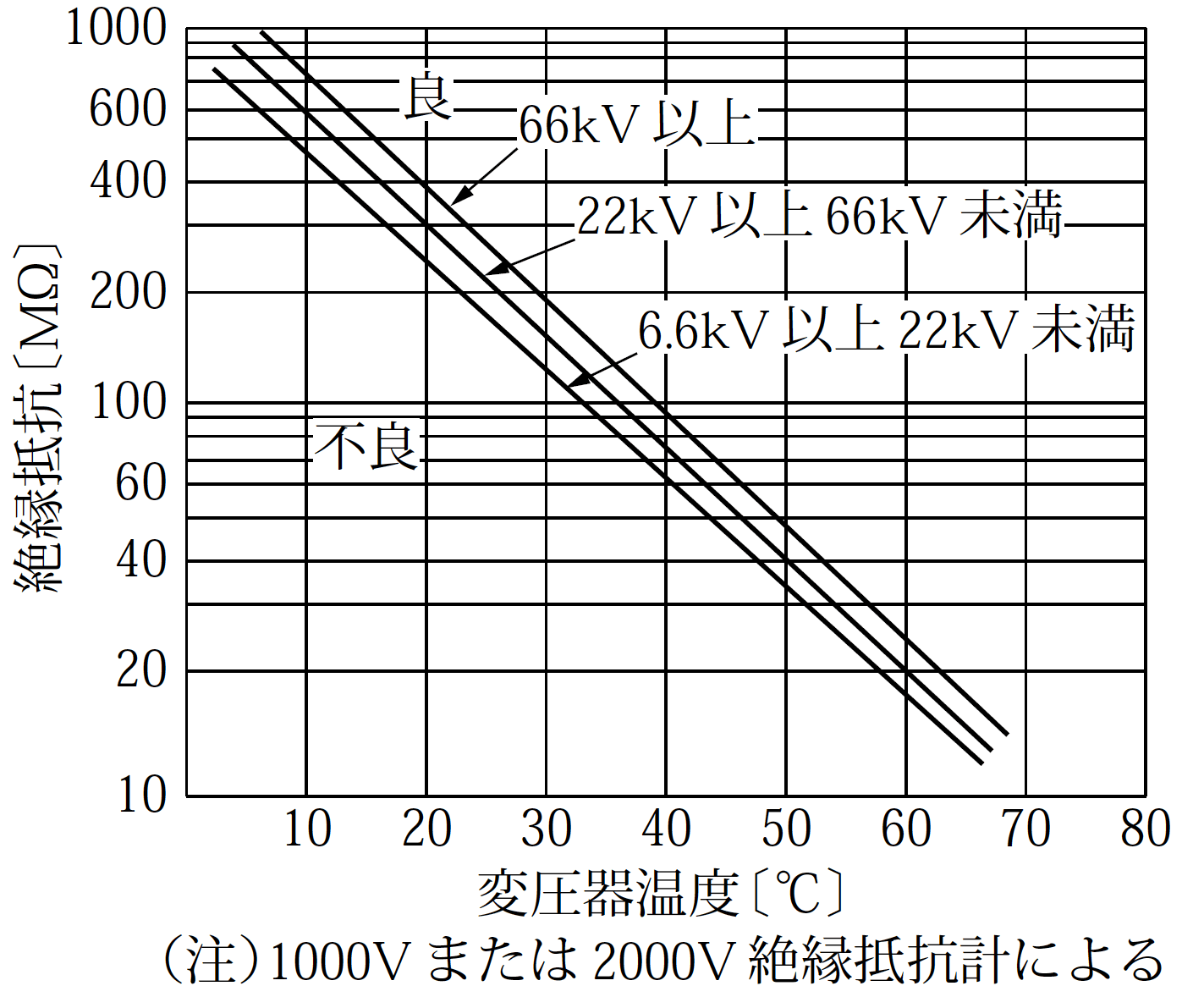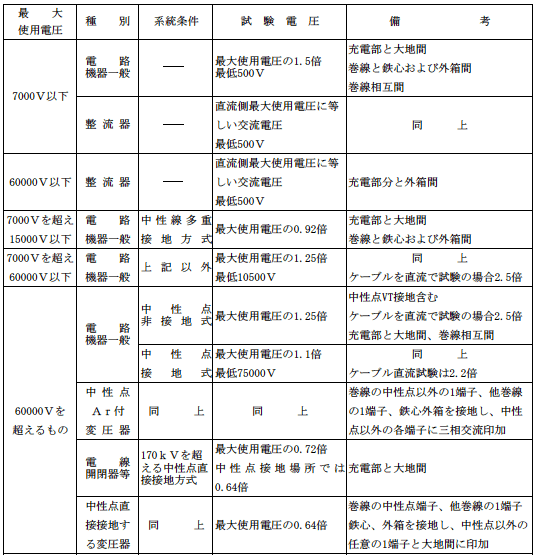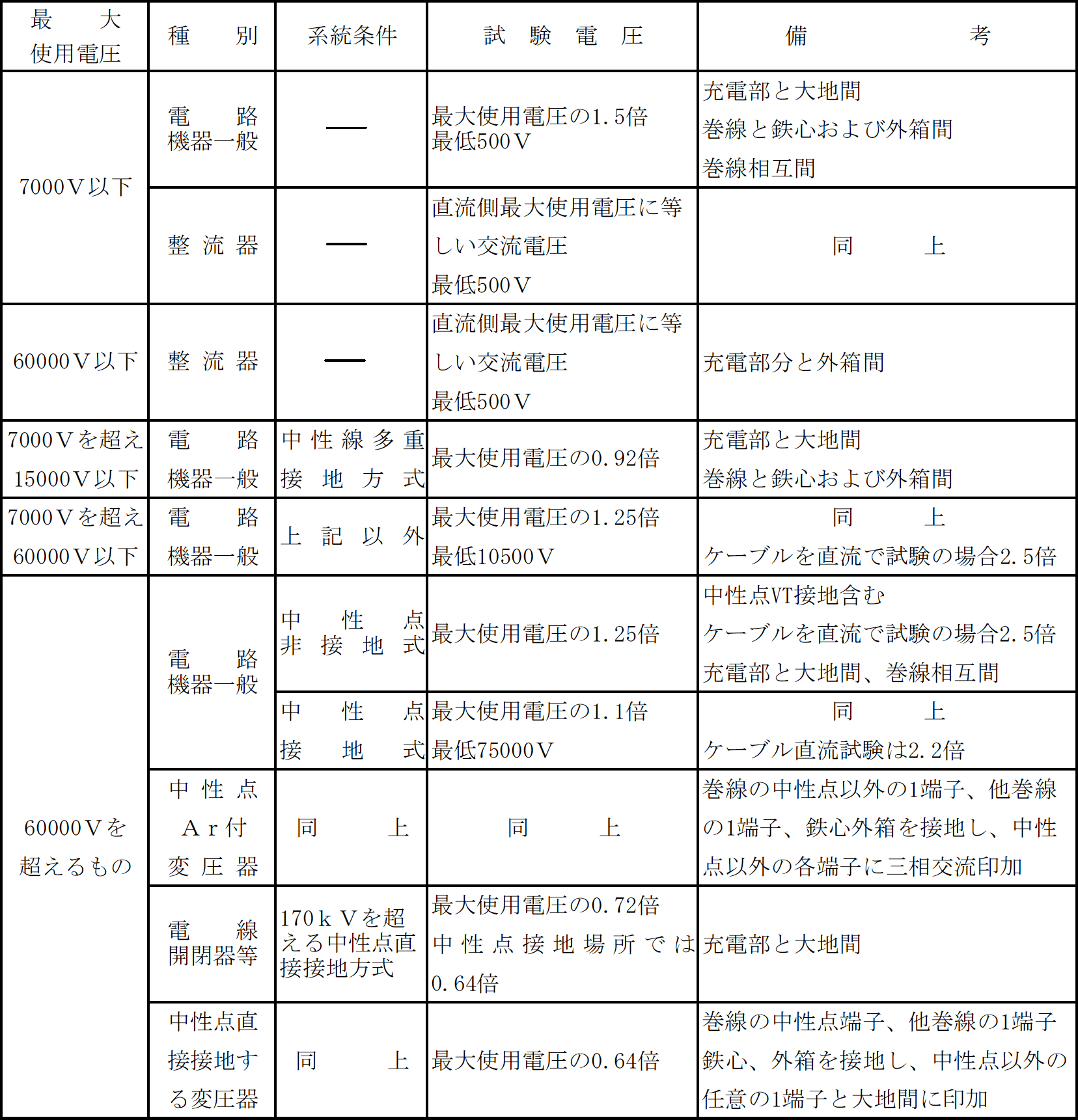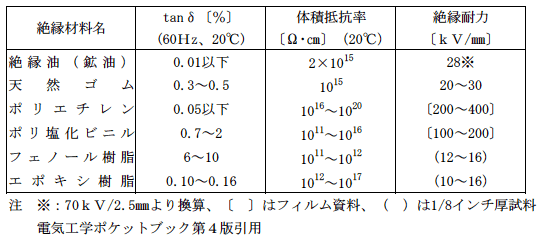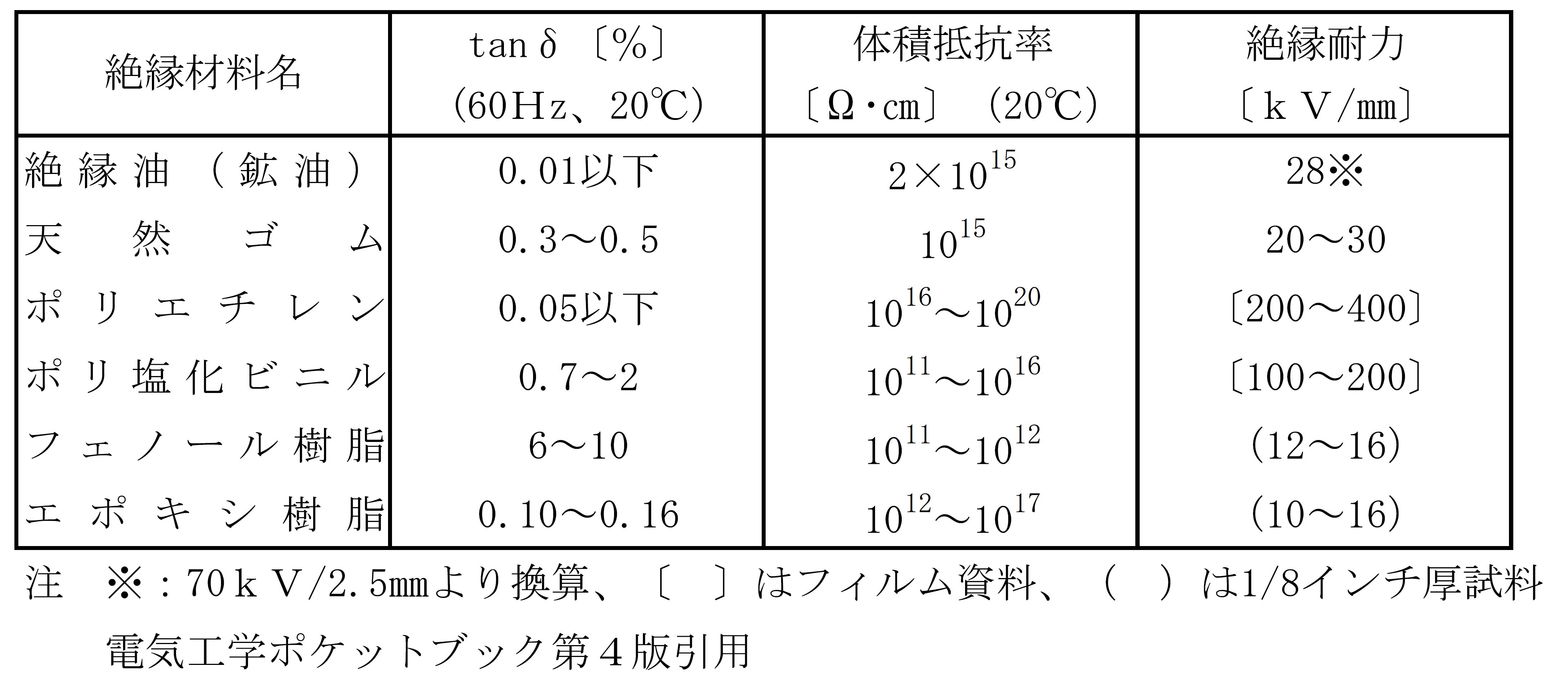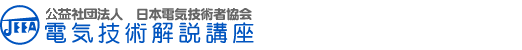



電気設備の絶縁状態把握のため、絶縁抵抗の測定と絶縁耐力試験が広く行われています。電気設備の技術基準でも低圧電路には絶縁抵抗値で、高圧、特別高圧では耐電圧値で保持すべき絶縁性能が規定されています。しかし、実際に現場では絶縁抵抗の判定に対する過信のようなものと、絶縁耐力試験の保守管理上の実施にためらいのようなものが見受けられます。絶縁抵抗の定期的な測定による経年変化を捕らえることで絶縁破壊事故の未然防止に役立ています。ここでは両試験の基本的な相違や試験電圧の決め方、判定基準などについて解説します。
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your
Flash plugin.

絶縁抵抗とは
絶縁物に直流電圧を印加すると、ごくわずかの電流が流れます。この電流と印加電圧の比を絶縁抵抗としていますが、この電流は絶縁物を貫通する電流と絶縁物の表面を流れる電流の合計です。
体積抵抗率(固有絶縁抵抗)は貫通電流を対象としたものですが、一般に絶縁物の表面を流れる電流のほうが多くなっています。
このため、絶縁抵抗の測定にあたっては一般にガイド端子を構成しますが、
電力ケーブルでは測定端とともに反対端のガイド端子も構成する必要があり、また、コンパクトに組み立てられているキュービクル内の機器や支持がいしなどには完全なガイド端子の構成は困難で、サンプル試験などのほかは沿面漏れ電流の完全な分離は不可能に近いものです。
また、最近の絶縁抵抗計ではガード端子を備えていないものも多くなっています。この沿面漏れ電流のため、絶縁抵抗の測定では雰囲気条件の影響を強く受けます。特にがいしやブッシングなどの表面に埃などが付着している場合は吸湿などの影響が大きくなります。
したがって、測定時の天候、気温、湿度、使用測定器の仕様などの記録のない測定値は無意味といってもよいぐらいです。
ただし、体積抵抗率(固有絶縁抵抗)は吸湿によって大幅に低下する特性があり、
このことが絶縁抵抗の測定によって絶縁特性の低下を監視する上で有効であるゆえんであり、効果的な絶縁監視のために定期的な測定によって経年変化を捕らえることで絶縁破壊事故の未然防止に役立て得る根拠です。
なお、絶縁抵抗は温度係数が負であり、また、電圧特性も一般的に負です。
以上の諸事項は絶縁抵抗測定値から絶縁性能を判定する上で十分配慮しておくべきことです。
規定及び判定基準
技術基準では、引込線を含む供給用低圧電線路と大地間及び電線相互間の絶縁抵抗は、漏れ電流が最大供給電流の1/2000を超えないようにと定められ、
使用場所の低圧電路では開閉器などで区切ることのできる電路ごとに第1表の値が定められています。
この場合で絶縁抵抗測定が困難なときはそれぞれ漏れ電流を1mA以下に保つように定められています。これは停止が困難な設備に対するもので、クランプメータにより活線で容易に測定できる利点があります。
この1mAという値は人体に流れたとき電撃を感じる最小値程度であり、また、
1箇所に集中して流れても火災などのおそれのない値です。漏れ電流による規定もまた絶縁抵抗による規定にほかなりません。
また、回転機については次の2式が古くから目安として参考にされています。
油入の変圧器、計器用変成器についての目安として第1図があります。
ただし、これらは高圧、特別高圧についてはあくまで目安として参考にするものです。また、特に電力ケーブル、計器用変成器などは、各相の製造条件、製造時期、使用経過が同一なので絶縁抵抗の各相のアンバランスに注意することが絶縁性能判定上極めて有効です。

耐電圧試験の意義
技術基準では、低圧電路の絶縁性能は絶縁抵抗の値で定められていますが、高圧以上では耐電圧値で規定されています。
低圧の電路、機器ではふつう250Vまたは500Vの絶縁抵抗計が使用されるため、これで測定された絶縁抵抗値でその絶縁性能としても間違いありませんが、高圧、特別高圧電路、機器では1000V〜2000Vの絶縁抵抗計による測定値はあくまで参考程度にしかならず、確実な絶縁判定は耐電圧試験によらなくてはなりません。
これは低電圧の絶縁破壊が、絶縁抵抗の低下箇所への漏れ電流の集中により、その部分の絶縁抵抗が更に低下し、漏れ電流が増加する悪循環によるものであり、これが沿面絶縁に起因すればトラッキング破壊になります。
これに対し、高圧、特別高圧では局部的な絶縁破壊がある程度進行すると、あとは放電現象としての絶縁破壊になるため、低圧電路の場合とは根本的に絶縁破壊の機構が異なります。
また、耐電圧試験は試験中の絶縁破壊を懸念することから現場では実施を懸念する傾向が多く見かけられます。
しかし、電気設備の技術基準には高圧、特別高圧の電路は「定められた電圧、方法による耐電圧試験に耐えること」(解釈第15、16条)と規定されています。
したがって、試験中に絶縁破壊するものは法的には使用してはならないものです。実際に試験資料として、いろいろな故障点を作ろうと絶縁体を傷つけたり、
部分的に破壊したりしても、技術基準に定められた耐電圧試験中に絶縁破壊するような資料を作り出すことは極めて困難です。
このことからも技術基準に定められた耐電圧試験中に絶縁破壊するものは既に重大な欠陥があり、時間の差こそあれ、使用中に破壊するものといえます。
運転中の絶縁破壊は保守管理上最も避けなければならないことで、このような危険な弱点箇所を摘出することも耐電圧試験の副次的な効果といえます。
試験電圧と試験時間
電気機器や電線路に発生する最も大きい異常電圧は雷撃に起因するものですが、これに直接耐える絶縁は不可能であり、侵入電圧の低減策がいろいろ講じられているほか、最終的には避雷器による保護に依存しています。
それ以外の日常発生する異常電圧に対しては機器、線路自体で耐えなければなりません。
耐電圧試験はこのことを確認するためのもので、設計上の耐電圧よりも十分低く、かつ、運転中に頻繁に発生する異常電圧に相当する程度の電圧を印加して絶縁耐力を確かめるものです。
対象となる異常電圧は主として1線地絡時の健全相の電圧上昇と開閉サージであり、その大きさは系統中性点の接地方式により大きく異なります。
また、絶縁耐力は


特性をもつため、試験電圧と印加時間は密接な関係があります。工場試験では古くから使用電圧の2倍の電圧を1分間印加することが行われていました。
技術基準では第2表の値で10分間耐えるものでなければならないと定められています。この試験電圧は系統中性点の接地方式で最大使用電圧に対する割合が異なっています。
更に電力ケーブルでは対地静電容量が大きく交流試験では所要電源容量、試験設備が大きくなり、試験が困難になるため交流試験の2倍の直流による試験が認められています。また、同様の理由から回転変流機以外の交流回転機も1.6倍の直流試験が認められています。(詳細は電技解釈第15、16条)
また、平成10年に「電路の絶縁耐力の確認方法 JESC-E7001 1998」が制定され、これにより、JEC、JISに規定に基づき工場において耐電圧試験を実施したものは技術基準による絶縁性能を満足しているものとして、輸送、現地組立て後の確認試験として、常規対地電圧を10分間印加すればよいことになりました。言い換えればこの条件を満たしていれば使用系統に接続して10分間異常がなければ使用してよいということです。
これは工場で実施される1分間の試験電圧が10分間に換算しても技術基準の規定電圧より十分上回ったものであることと、最近の設計、施工技術の進歩により、輸送や組立て段階での品質低下がほとんどなくなったことによるものです。

高絶縁抵抗必ずしも高絶縁耐力ではない
冒頭述べたように技術基準では低圧の電路、機器については絶縁抵抗で、高圧、特別高圧のものについては絶縁耐力で絶縁性能を規定しています。
これは一般に絶縁抵抗が大きければ絶縁状態は良好としていますが、高絶縁抵抗が必ずしも高耐電圧とは限りません。
このことは空気絶縁の例をみれば明らかで、1000V絶縁抵抗計のリード線の間隔を2〜3mmとして、その間の絶縁抵抗を測定すれば測定値は無限大を示しますが、この間げきに電圧を印加すれば数千Vでフラッシオーバ(絶縁破壊)します。すなわち、無限大の絶縁抵抗があっても、耐電圧値は数千Vということです。
固体絶縁物についても体積抵抗率と絶縁耐力とは必ずしも密接な相関にはありません。よく使用される絶縁材料の特性を第3表に示します。
最も我々に親しみ深い塩化ビニルを例にとれば、tanδはポリエチレンの約20倍と悪く、体積抵抗率は1万分の1程度ですが、絶縁耐力は1/2ぐらいです。
以上電路、機器の現場での絶縁判定にあたっての絶縁抵抗測定と耐電圧試験について述べましたが、両試験は設備の保守管理上極めて重要なものです。
また、両者の特質についても述べましたが、実際に現場での効果的な絶縁判定をする上で、特に絶縁抵抗への過信と耐電圧試験への不信の解除について幾分でも参考になれば幸いです。